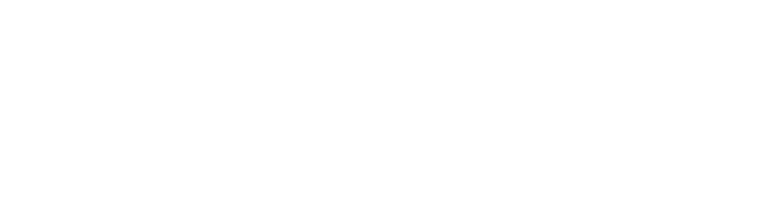2011.09.29 : 平成23年_第3回定例会
「緩和医療」
◯副議長(鈴木貫太郎君) 二十三番早坂義弘君。
〔二十三番早坂義弘君登壇〕
◯二十三番(早坂義弘君)
余命半年。ある日、末期がんだと告知され、残りの人生が六カ月だとわかったら、その半年間をどう過ごすでしょうか。私なら、告知を受けた直後はショックでしばらく寝込むかもしれません。しかし、すぐに思い返して、海外旅行に行き、おいしいものを食べ、最期は愛する家族に囲まれながら、ありがとうといって、がくっと絶命する。そんなふうにして過ごしたいと思います。
しかし、先日お会いした東邦大学大森病院の大津秀一先生からは、早坂さんが思う最期はまるでテレビドラマのようですが、そのような死に方をする人は一人もいませんといわれました。現実には、抗がん剤の副作用で食欲が低下し、何を食べても砂をかむように感じる。せん妄という精神的混乱状態が発生し、大声で家族に暴言を吐く。そんな姿を見るのはつらいから、見舞いに来る家族の足が遠のく。延命のために人工呼吸器などの機械や管がどんどん体に取りつけられていく。私の理想からはかけ離れた、こういう状態で死に行く人が多いそうです。思い返してみると、私自身、ご遺体と対面したことなら何度もありますが、人がまさに死に行く姿を、実は一度として見たことがありませんでした。
がんは痛いといいます。それについても尋ねました。大津先生は、適切なケアを受ければ、がんの苦痛は劇的に違ってくるし、早坂さんの理想の終末期に近づけることもできると断言しました。これが緩和医療と呼ばれるものです。
緩和医療は、がんを治す治療ではありません。患者の苦痛を軽減させるための医療です。
しかしながら、今日、我が国でこの緩和医療が十分に提供されているとはいえません。緩和医療に不可欠の医療用麻薬の、国民一人、一日当たりの使用量がアメリカの二十分の一だということを見てもわかります。ちなみに、麻薬というと注射のイメージがありますが、今日では錠剤が主流で、中には張り薬もあるそうです。
我が国で緩和医療の提供が十分ではない理由は二つです。
一つ目は、患者や家族の緩和医療に対する誤解です。苦痛を軽減させる緩和医療とがんを治す治療とは併用可能であって、決してどちらか一つしか選択できないものではありません。しかしながら、緩和医療といわれたら、あとは死ぬだけという間違った思い込みから、緩和医療を拒否する患者すらいると聞きます。モルヒネは終末期患者の頭をおかしくせず、命も縮めず、痛みだけを取るという、すばらしい効果を発揮します。緩和医療とはどういうものか、都民に対して、正しい理解を促していく必要があります。
緩和医療の提供が十分でない理由の二つ目は、緩和医療の臨床に秀でた医師、看護師の不足です。昨年、都内で亡くなったがん患者は三万二千人。これに対し、緩和医療専門医は、二年間で全国二十四人しか生まれていません。若手の医師、看護師に緩和医療を教育できるスタッフが、そもそも少ないのです。
余命半年と宣告された後、どんなに病気が苦しくても少しでも長く生きたいか、あるいは苦痛を伴う延命治療を拒否するか。このリビングウィルに関して、日本尊厳死協会が、みずからの意思を示すためのマニュアルを公開しています。しかし、それが現実に一〇〇%尊重されるかといえば、それは甚だ微妙です。
というのも、特に延命拒否の意思は、生命の長さが最優先という医療現場の常識があるゆえに尊重されにくいからです。家族からすれば、やはり長く生きてほしいと思うでしょうし、医療者の立場からすれば、裁判ざたになることに対しての備えという側面もあります。その意味で、延命拒否の意思を持つならば、これに対する事前の十分な意思疎通が患者、家族、医療者の間で必要です。
家族に迷惑をかけないならば、みずからに残された最後の時間は、病院ではなく住みなれた自宅で過ごしたいと思います。そのことを先ほどの大津先生に伺いましたら、患者が自宅に戻りたいのなら、在宅で緩和医療を受けるのがいいし、それは可能だとおっしゃいました。そもそも緩和医療とは、単に肉体的な苦痛に限らず、広く精神的なものまで含んだものであります。実際、自宅に帰りたいという希望をかなえるだけで、苦痛のある部分が軽減され、モルヒネの投薬量が減るケースがほとんどだそうです。人生は長ければ長いほどいいか、短くとも充実を求めるか、人生いろいろだと思います。しかし、そのどちらであっても、緩和医療は、人生最期のときを満ち足りたものにする手助けになります。
そこで、がん終末期患者のクオリティー・オブ・ライフと緩和医療に対する知事のご見解を伺います。
〔知事石原慎太郎君登壇〕
◯知事(石原慎太郎君)
早坂義弘議員の一般質問にお答えいたします。
まず、がんの終末期患者の緩和医療についてでありますが、医学が進歩した現代にあっても、人は必ず老い、そして、やがては死んでいくものであります。ソルボンヌ大学の哲学の主任教授のジャンケレヴィッチの死に関する非常に興味深い分析の本がありますが、その中にも、死は人間にとって最後の未来であると書いてありますけれども、しかし、それが未来であるがゆえに、この自分が必ず死ぬということを信じている人間は余りいないわけであります。
がんによる余命宣告は、こうした自分の死といや応なく向き合うことを強いるわけでありまして、また、がんの進行は痛みを伴い、気力や体力を徐々に奪うものでしょう。終末期患者の緩和医療は、死の恐怖がもたらす心理的な苦痛や痛みからくる身体の苦痛をできるだけ取り除く医療であり、死と向き合うことを支援する医療でもあります。
しかしこれが、ご指摘のように、専門家が少ないゆえに、余り日本の社会で敷衍していない。そういうことで、例えば私の知己でもありました、すぐれた作家の吉村昭君は、何度目かのがんの末期にたまりかねて、もういいということで、自分で自分の延命装置を引きちぎって外して、自分で死を選びましたが、そういう悲劇というのでしょうか、そういう無残な出来事も、数を減らすことにつながると思います。
死をいかに迎えるか、これを受け入れるかは、個々の人の人生観にもよるものでありますが、緩和医療は最期までその人らしい人生を全うするための手だてになるに違いないと私も思います。